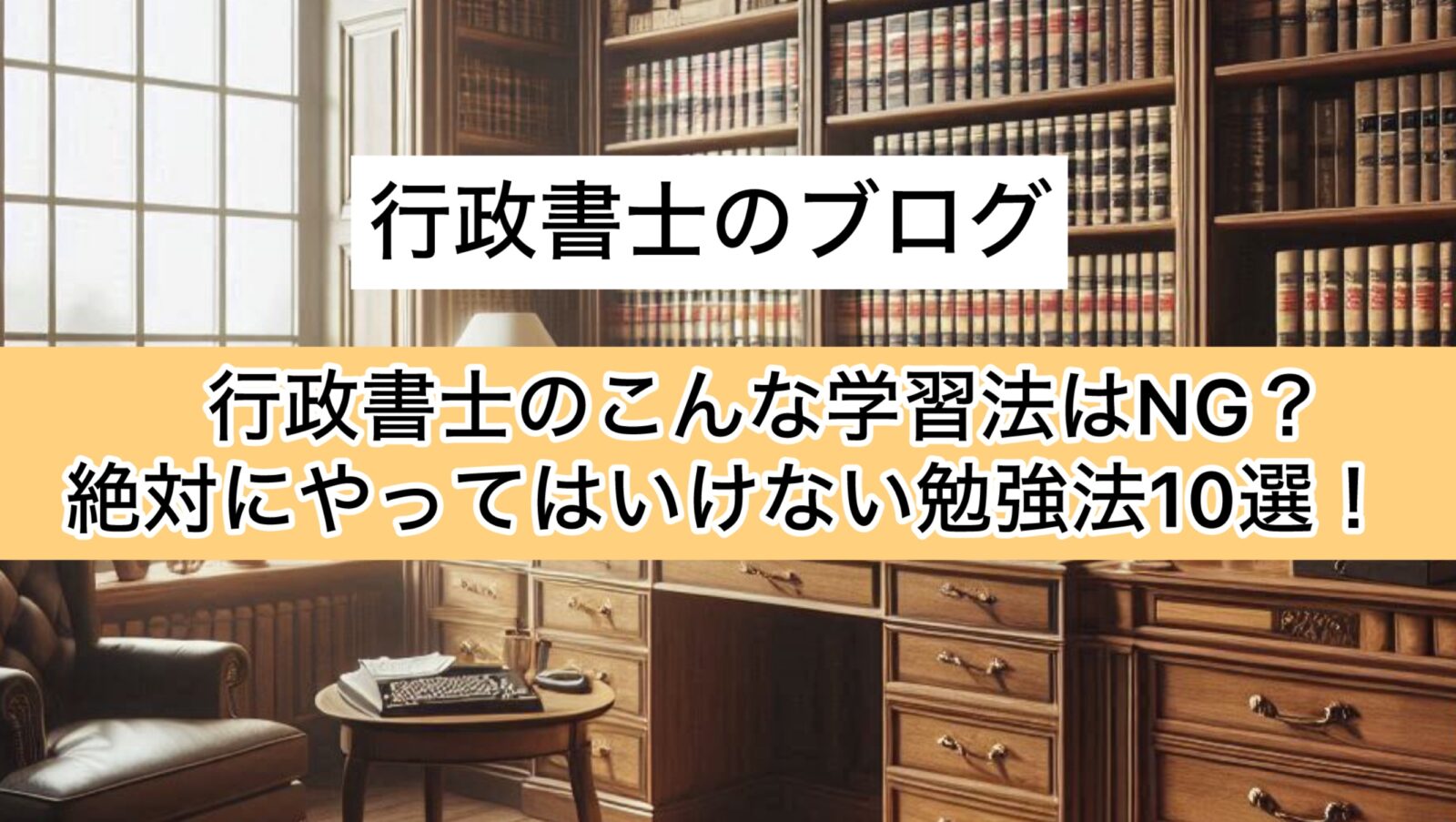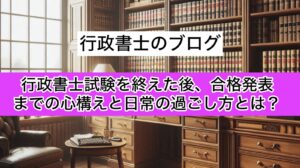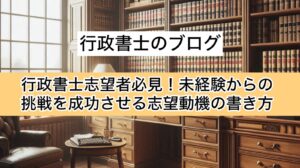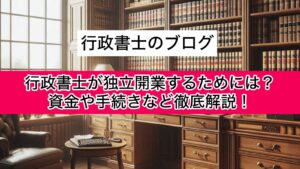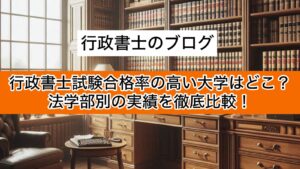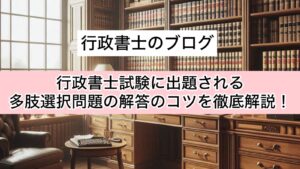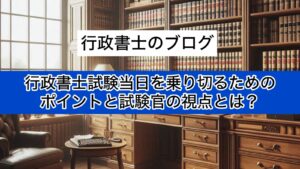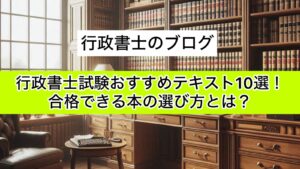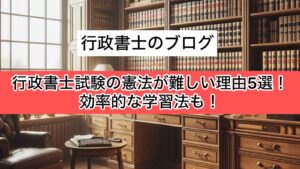行政書士試験を受験するのはいいけど、試験で合格が遠のいてしまうのは、なんだか切ない気持ちになってしまいますよね。
そんな方の為に、今回の記事では、行政書士試験に合格する為の最短ルートである、「こんな学習法はNGだ!」というテーマで、特に注意してほしい10の学習法についてお話しします。
この10個はランキング形式ではなく、皆さんに気をつけてほしいポイントをお伝えするものです。
まず、NGと聞くと「何を偉そうに」と感じる方もいるかもしれません。そこで、まずは「こういう学習をした方が良い」という前提をお話しした上で、どのような学習法がNGなのかをお伝えしていきます。
行政書士試験で絶対にやってはいけない勉強法10選!
行政書士を目指して頑張ってるのに、試験の合格が遠のくのは絶対に避けたいものですよね。
以下は、行政書士試験で絶対にやってはいけない勉強法10選をご紹介しているので、1つ1つしっかり学んでいきましょう!
やってはいけない勉強法①:全体像を把握せずに立ち止まる学習法
まず、始めに1つ目のポイントは、全体像を把握せずに立ち止まる学習法です!
特に初めて勉強する場合、知らない用語や言葉がたくさん出てきます。そのたびに立ち止まって調べる人がいますが、特に民法のような科目では、前に出てくる内容が後から出てくることもあります。したがって、多少分からなくても最後まで一気に進めることが重要です。全体像を把握することが大切ですので、1周目は早く全体を回すことを心がけましょう。このように、理解するまで進まない学習法はNGですので、注意してください。
やってはいけない勉強法②:条文を軽視する学習法
次に、2つ目のポイントは、条文を軽視する学習法です!
法律の学習において最も重要なものはテキストや過去問ですが、合格者は条文六法を大切にしています。六法がボロボロになるほど使い込むことが重要です。最初は出てきた条文をチェックするだけで構いませんが、後で見返したときにチェックが入っていることに気づくこともあります。条文を大切にしない学習法はNGですので、注意が必要です。
やってはいけない勉強法③:モチベーションに左右される学習法
次に、3つ目のポイントは、モチベーションに左右される学習法です。
行政書士試験の勉強は長期間にわたりますが、人間には気持ちの浮き沈みがあります。合格者はその日の気分に左右されず、毎日決まった時間に勉強を習慣化しています。朝5時に机に向かい、テキストや条文を開いて講義を受けたり過去問に目を通したりすることがルーティンになっています。モチベーションに左右される学習法はNGですので、習慣化を目指してください。
やってはいけない勉強法④:直前期の学習法と情報集約
さて、4つ目のポイントは、直前期の学習法と情報集約です。
行政書士試験において、最も合格を左右する時期はいつでしょうか?もちろん、1年間の勉強全体が重要ですが、特に重要なのは9月以降の直前期です。この時期が合格を大きく左右します。したがって、9月以降の直前期には余計なことをしている暇はありません。この直前期に向けて、日々の学習の中で自分が必要とするテキストや過去問、条文、問題集の状態を意識しておくことが重要です。
合格者がよく行っているのは「情報集約」です。情報が整理されていることが大切です。例えば、過去問の知識がテキストのどの部分に関連しているかをメモしておくことが有効です。「この過去問の知識はテキストのP162に書いてある」といった具合に、簡単にメモを残すだけで良いのです。
また、問題集を解く際に、1回目や2回目に分からなかった問題には印をつけておくことが重要です。全体が分からない場合は、その問題全体にバツをつけたり、太い線を引いたりしておきます。しかし、特定の選択肢が分からない場合は、その選択肢にシールを貼ったり、ボールペンでチェックを入れたりすることが効果的です。100均で売っている細いポストイットを使って、選択肢の外にはみ出るように貼ると、最終的に分からない選択肢が明確になります。これも情報集約の一環です。
直前期にこれらの情報が整理されていると、勉強が格段に効率的になります。合格者は皆、この情報集約を意識しています。したがって、情報集約を全く意識しない学習法はNGですので、注意が必要です。
やってはいけない勉強法⑤:過去問の正しい使い方
次に、5つ目のポイントは、過去問の正しい使い方になります。
合格者は過去問の使い方を間違えていません。過去問を何度も解いて、答えを覚えてしまったから意味がないと考えるのは間違いです。過去問は10回、15回繰り返しても、ただ答えを覚えるだけでは不十分です。
過去問を解いたら、その問題に関連する条文を引きましょう。例えば、即時取得に関する問題が出た場合、関連する192条を確認し、その後193条や194条も見てみることが重要です。問題では問われていない他の論点や判例も確認することで、過去問を通じてどの分野がよく出題されるのか、どのように問われるのかを理解できます。
過去問は1つの問題を解くことで、条文や判例についても学ぶことができるため、非常に効率的です。過去問の使い方を間違えないようにしましょう。
やってはいけない勉強法⑥:SNS時代の情報収集と合格者の学習法
さて、続いて6番目のポイントが、 SNS時代の情報収集と合格者の学習法です!
これは実は、アガルート時代やレク時代からの経験に基づいています。約20年近く様々なことをやってきましたが、特にここ10年、あるいは7〜8年の間に顕著になってきたことがあります。それは、SNSの発展です。今やSNSが普及しているため、さまざまな情報が溢れています。例えば、行政書士試験について「こうすればいい」とか「この講師が良い」といった情報が次々と出てきます。
これ自体は悪いことではありませんが、合格者はどのように情報を扱っているかというと、彼らは特定の学習法や教材に一貫して取り組んでいます。テキスト、条文、過去問、問題集、模試を含めた学習がしっかりと行われており、これらの教材がボロボロになるまで使い込んでいます。合格者は「これでやる」と決めたら、その方法を信じて突き進んでいます。
しかし、SNSの情報に振り回されてしまうと、「私の勉強法は間違っているのではないか」と不安になってしまうことがあります。合格者は基本的に情報に振り回されず、うまく利用しています。つまり、情報に振り回されすぎることは非常に危険ですので、注意が必要です。
やってはいけない勉強法⑦:合格者の暗記法
次に7番目のポイントは、合格者の暗記法です。
資格試験である以上、これは行政書士試験に限らず、他の試験でも同様ですが、覚えるべきことはしっかりと覚えなければなりません。
合格者は、落としてはいけない知識を徹底的に暗記しています。合格者がなぜあれほど多くの知識を持っているのか、不思議に思うかもしれませんが、実際には何度も繰り返し学習しているからです。
合格者は、1周目の段階ではおそらく20%から30%程度しか覚えていませんが、繰り返し学習を行うことで、知識が定着していきます。暗記という言葉は嫌われがちですが、資格試験においては覚えることが不可欠です。したがって、暗記から逃げることはNGです。最終的には、覚えるべきことはしっかりと覚えなければなりません。
やってはいけない勉強法⑧:スケジューリングの重要性
8番目のポイントは、スケジューリングの重要性についてです。
合格者の方達が共通してしっかりとしたスケジューリングがあります。手書きの手帳を使う人もいれば、Excelで管理する人もいますが、皆、直前期から逆算して計画を立てています。
例えば、9月1日までにこの状態に仕上げたいと考えた場合、逆算して必要な時期にどの程度の進捗が必要かを考え、1日あたりのノルマを設定しています。合格者は直前期のスケジューリングも厳密に立てており、これが合格のポイントとなります。
もちろん、仕事や家庭の事情でスケジュールがずれることもありますが、リスケは全然問題ありません。重要なのは、万全に勉強を進めるためにしっかりとしたスケジューリングを行うことです。
やってはいけない勉強法⑨:焦点を絞る重要性
9つ目のポイントは、焦点を絞る重要性です。
合格者は、一つのテキストを徹底的に使い込むことが非常に重要です。多くの教材に手を出すことは、知識が分散してしまい、結果的に理解が浅くなってしまう可能性があります。特に直前期には、焦点を絞って一つの教材を深く掘り下げることが求められます。
手を広げすぎると、自分のキャパシティを超えてしまい、逆に学習効率が下がってしまいます。合格者は、特定のテキストをボロボロになるまでやり込むことで、知識を定着させています。このように、質の高い学習を行うためには、教材を厳選し、深く学ぶことが大切です。
したがって、勉強を進める際には、手を広げすぎず、一つの教材に集中して取り組むことを心がけましょう。これが合格への近道です。
やってはいけない勉強法⑩:精神論の重要性
さて、いよいよ最後の10個目のポイントです。ここでは精神論の重要性についてお話しします。
これは特に直前期に関する話です。過去の合格者の中で共通して言っていることは、「絶対に諦めませんでした」ということです。合格点を模擬試験で一度も取れなかった人もいますが、「やめようかな」と思った瞬間もあったけれど、「今年こそは合格したい」と思い、諦めなかったのです。
合格者は、合格点を超えたり超えなかったりを繰り返しながら、時には一般知識で足切りになってしまった人もいます。それでも、彼らは「絶対に受かりたい」と思い続け、諦めなかったのです。これは本当に全ての合格者に共通する姿勢です。つまり、最後は精神論に行き着くのです。
ここで言いたいのは、諦める心持ちはNGだということです。スラムダンクの安西先生の言葉を思い出してください。「諦めたらそこで試合終了」です。この言葉は資格試験においても非常に重要です。絶対に諦めてはいけません。
以上が、合格者倍増中の行政書士試験に向けた学習法のNGポイントです。これらを意識して、効果的な学習を進めていきましょう。
まとめ
今回は、行政書士試験の合格が遠のく?絶対にやってはいけない勉強法10選!と言うテーマでご紹介しました。
今回のNGな勉強法10選を理解するだけでも、試験に向けて、スムーズに勉強が捗ります。
行政書士試験に合格する為には、どういった勉強法がだめなのかをしっかり理解していくのも大事なことですが、同時に正しい勉強法を理解するのも重要です!
次回の記事では、そういう正しい勉強法についてもお伝えしていきますね。
最後までお読みいただいてありがとうございました!
それでは!