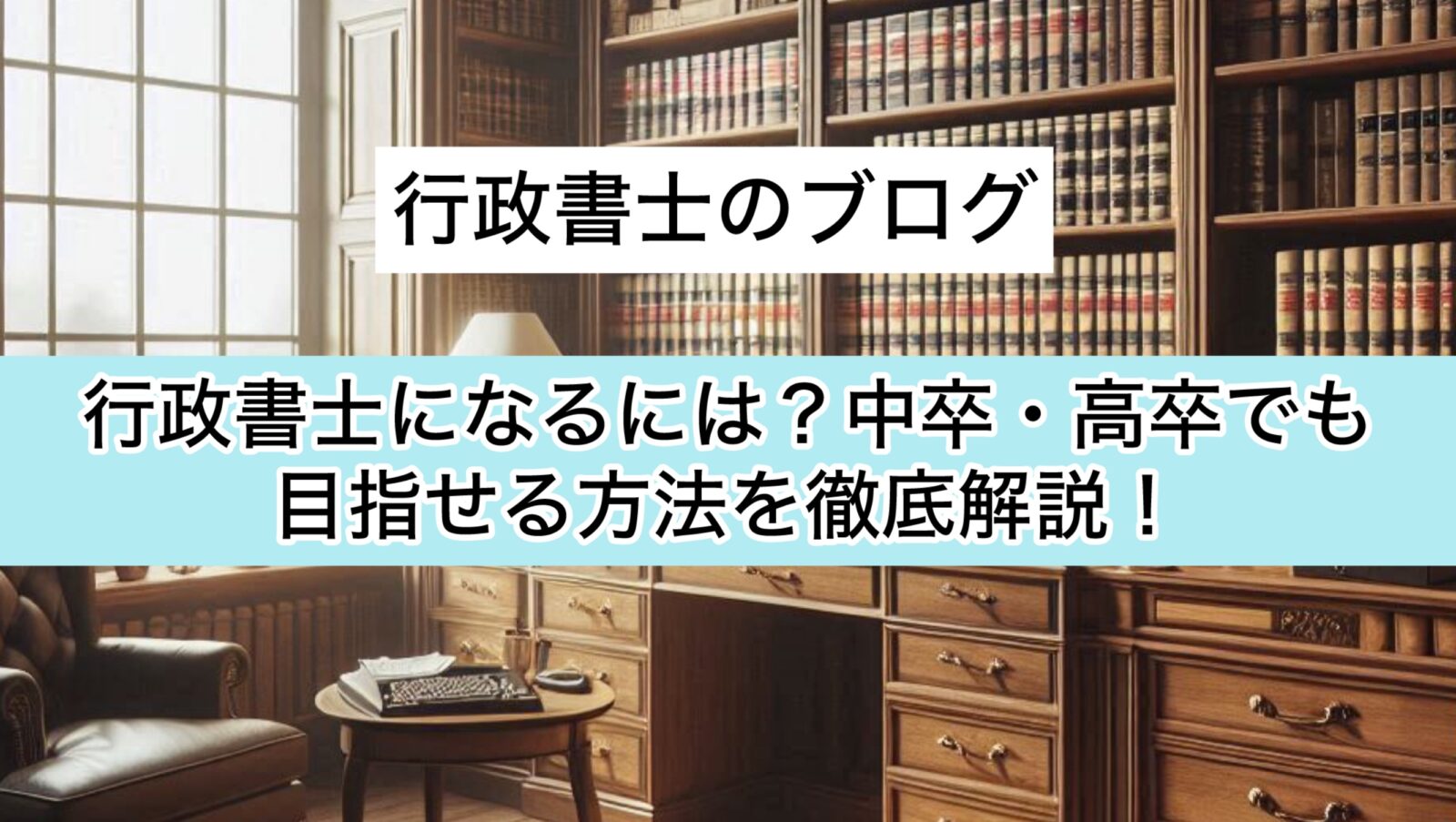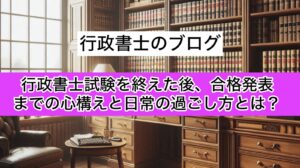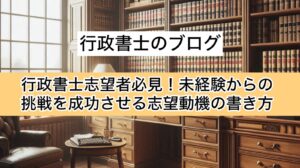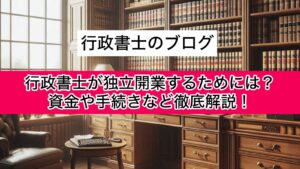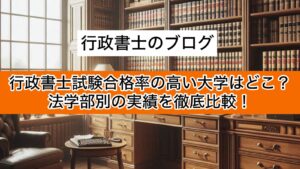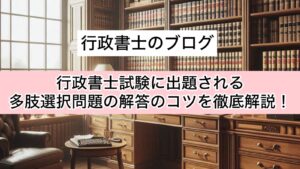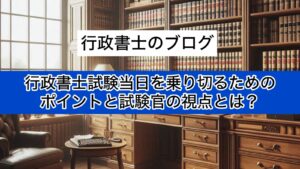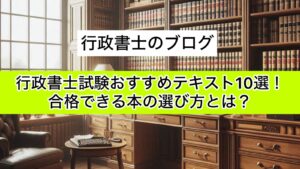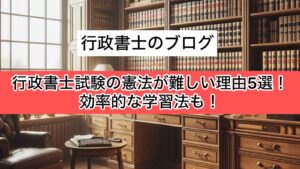行政書士になりたいけど、学歴とか関係あるのかな?とか、中卒や高卒でも目指せるのかな?って、不安に思う方もいるかもしれませんね。
実は、行政書士試験は学歴や年齢に関係なく誰でも受験できるんです!
私も最初は「難しそう…」と思っていましたが、意外とコツコツ勉強すれば道は開けるものです。
今回の記事では、行政書士になるためにどういうステップを踏んでやっていくのか、又、中卒や高卒でもなれるのかをご紹介していきます。
具体的な方法や試験のポイント、合格後の流れなども、できるだけ分かりやすくお伝えしていきますので、少しでも参考になれば嬉しいです!
行政書士になるには?
結論からお伝えすると、行政書士になるには、まず行政書士試験に合格することが必要です。
この試験は学歴や年齢に関係なく誰でも受けられるので、「中卒や高卒だけど大丈夫かな?」という方でも安心してくださいね。
私の場合は、法律なんて全然知らない状態からスタートしましたが、市販のテキストや過去問を繰り返し解くことで少しずつ理解できるようになりました。
試験は毎年11月に行われていて、合格率は10%前後なので簡単ではありませんが、計画的に勉強すれば十分合格を目指せます。
ちなみに、行政書士になる方法は試験だけじゃなくて、公務員として一定期間行政事務に携わった人が資格を取得できる「特認制度」というものもあります。
具体的に言うと、行政書士資格の「特認制度」というのは、長年公務員として働いてきた人が、試験を受けなくても行政書士の資格を取れる仕組みのことで、高校を卒業してから17年以上、または中学を卒業してから20年以上、公務員として行政に関わる仕事をしてきた人が対象になります。
この制度がある理由は、公務員としての仕事で得た経験や知識が、行政書士としての仕事にも役立つと考えられているので、そのため、試験を免除して資格を与える仕組みが設けられています。
また、弁護士や税理士の資格を持っている方は試験を受けずに登録することも可能なんです。
試験に合格したら、行政書士会への登録手続きをして、事務所を開設すれば晴れて行政書士としてスタートできます!
最初は不安かもしれませんが、一歩ずつ進めればきっと道は開きます。
行政書士になるために、中卒・高卒でも目指せる?
行政書士になりたいけど、「中卒や高卒だと難しいんじゃないか…」と不安に思っている方もいるかもしれませんね。
でも、安心してください!
冒頭でもお伝えしましたが、行政書士試験には受験資格がないので、学歴や年齢は一切関係ありません。
実際に、中卒や高卒の方でも合格して活躍している人はたくさんいます。
私も最初は「法律なんて難しそうだし、自分にできるのかな?」と思っていましたが、コツコツ勉強を続けていけば必ず道は開けると感じました。
私が思うに、中卒や高卒だからといって特別なハンデがあるわけではないので、むしろ、合格するためには「どう勉強を続けるか」が一番重要になってきます。
行政書士になるために、中卒・高卒でも合格できるポイントとは?
ここからは、中卒・高卒でも行政書士試験に合格できるポイントなどを、私自身が感じた事をいくつかお伝えしていきますね。
中卒・高卒でも合格できるポイント①:基礎から始める
中卒・高卒でも合格できるポイント1つ目は、まずは基礎から始めることです!
最初は法律用語や試験範囲の広さに圧倒されるかもしれません。
でも、焦らず基礎から始めれば大丈夫です。
私の場合は、市販の入門書を読んで「憲法ってこういうものなんだ」とか「民法って意外と身近な話なんだな」と理解するところからスタートしました。
中卒・高卒でも合格できるポイント②:過去問を繰り返す
中卒・高卒でも合格できるポイント2つ目は、過去問を繰り返すことです!
行政書士試験では、過去問が本当に重要です。
最初は全然解けなくてもいいので、とりあえず問題を見てみることから始めましょう。
私も最初は全然分からなくて落ち込みましたが、何度も繰り返すうちに少しずつ慣れてきました。
中卒・高卒でも合格できるポイント③:自分のペースで続ける
中卒・高卒でも合格できるポイント3つ目は、自分のペースで続けることです!
中卒や高卒だからといって、特別な方法で勉強する必要はありませんが、ただ、自分のペースで無理せず続けることが大切です。
私は仕事をしながら勉強していたので、「今週は1時間だけ」とか、「来週は2時間挑戦してみよう」とか、そういった感じで、来週、再来週に勉強する時間などのスケジュールを決めて取り組んでいました。
それでも少しずつ知識が積み上がっていきますよ。
行政書士試験に合格した後の流れや手続きは?
行政書士試験に合格した後、次のステップとして「行政書士として活動するかどうか」を決めます。
活動する場合、都道府県の行政書士会に登録する必要がありますが、登録せずに資格を活かして転職やキャリアアップを目指す選択肢もあります。
ここでは、合格から実際に行政書士として活動を始めるまでの流れを、順序立てて説明していきますね。
まず、試験に合格したら、自分の目指すキャリアプランをしっかり考えてみましょう。
行政書士として独立開業する場合や、事務所・法人に就職する場合は、都道府県の行政書士会に登録が必要です。
登録にはいくつかの手続きや費用が必要ですが、必要な書類には合格証明書、住民票、履歴書、誓約書などがあり、登録費用は約20~30万円程度です!
登録準備が整ったら、居住地の都道府県行政書士会に登録申請を行います。
申請後、審査を経て正式に行政書士として登録されますが、この審査には数週間から1ヶ月程度かかることが一般的です。
登録が完了すると「行政書士証票(バッジ)」と「登録番号」が交付され、これらは名刺や看板などに記載して自分が正式な行政書士であることを証明します。
登録後すぐに業務を始めることも可能ですが、多くの場合、実務経験やスキルが不足していると感じる人もいます。そのため、実務講座や研修に参加することで実務スキルを身につけることが重要です。
行政書士会や民間団体が提供する研修プログラムがあり、先輩行政書士の事務所で経験を積む方法もあります。
また、相続・遺言業務や許認可申請業務など、自分が取り組みたい分野について深く学びます。
スキルを身につけたら、いよいよ行政書士として本格的な活動をスタートします。
独立開業の場合、自宅や事務所を拠点として開業届を提出し、名刺やホームページなどで集客準備を整えます。
自分の得意分野を明確にし、それに特化したサービス展開も検討しましょう。
就職の場合、行政書士事務所や法人へ就職し、実務経験を積みながら働きます。
他の専門家(司法書士・税理士など)との連携も学べる環境でスキルアップすることも可能です。 さらにステップアップしたい場合は、「特定行政書士」の資格取得も検討しましょう。
特定行政書士になると、不服申立て手続きなど代理権限が拡大し、より幅広い業務が可能になります。この資格取得には、日本行政書士会連合会が実施する法定研修と考査試験への合格が必要です。
このように、一歩ずつ進んでいけば、行政書士として充実したキャリアを築くことができます。
まとめ
今回は、行政書士になるには?中卒・高卒でも目指せる方法を徹底解説!というテーマでご紹介しました!
行政書士になるには、まず、行政書士試験に合格することが必要です。
試験は学歴や年齢に関係なく誰でも受けられますし、中卒や高卒の方でも大丈夫です!
中卒・高卒の方でも試験に合格できるポイントとしては、「基礎から始める」「過去問を繰り返す」「自分のペースで続ける」という、この3つのポイントさえ抑えていれば大丈夫です。
あとは、しっかり日々行動をしていくことがなによりも重要ですので、自ら行動していかないと前には進みません。
ですので、日々の勉強する時間などのスケジュールをしっかり決めておいてくださいね。
私の場合は、自分のメモ帳に日々のスケジュールの予定などをぎっしり書いていました。
そうすることで、夜寝る前にメモ帳を見て、明日の予定は何をするのかが分かるので、メモ帳に記載しておくとスムーズに行動に移せます。
行政書士試験に合格した後は、行政書士として独立開業したい方、または、事務所・法人に就職する方は、都道府県の行政書士会に登録が必要になってきます。
行政書士として自分はどういう働き方をしていきたいのかを、事前に決めておくのも重要です。
最後までお読みいただいてありがとうございました!
それでは!