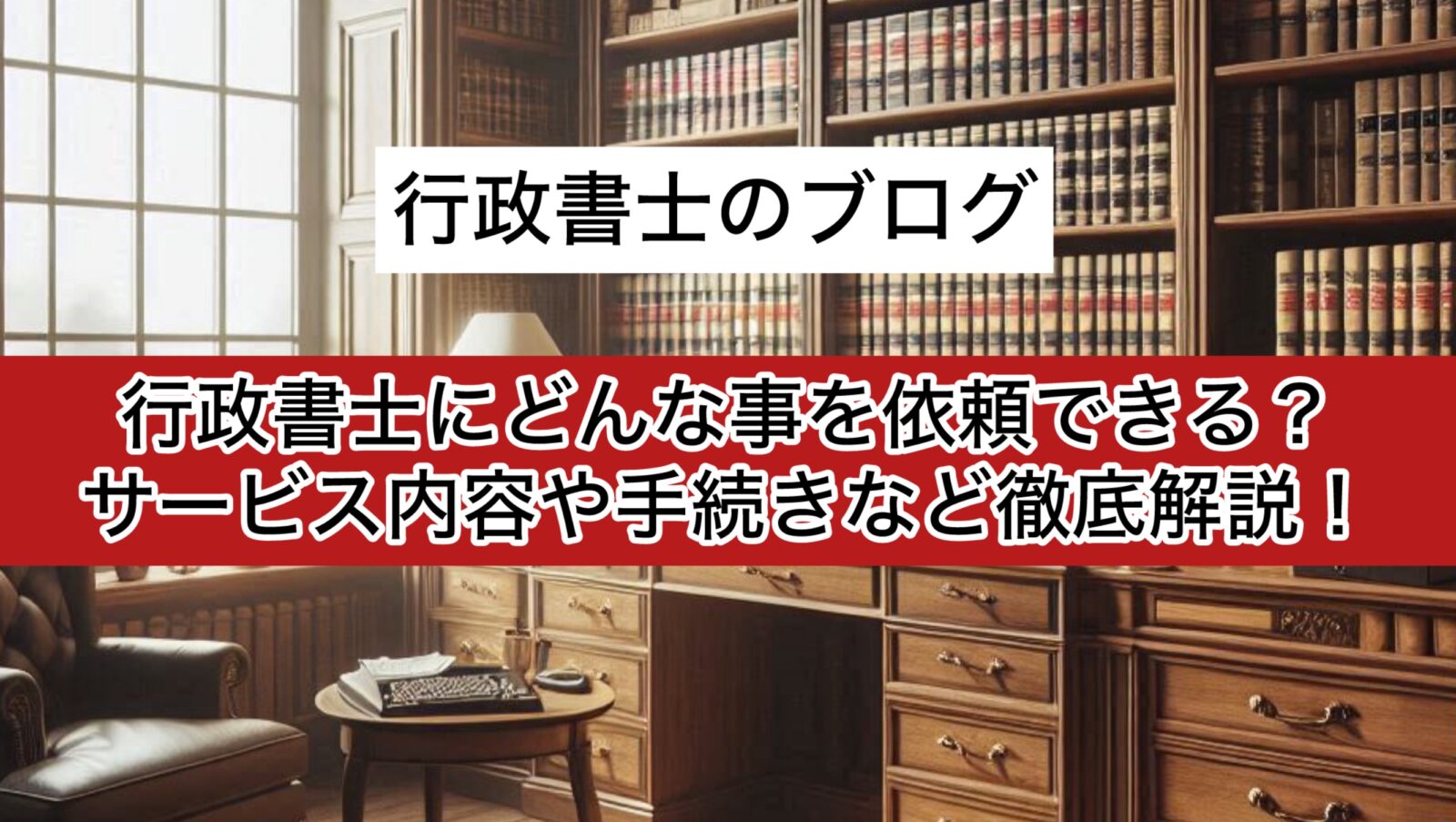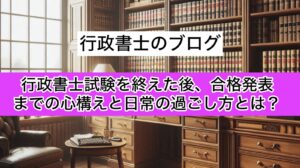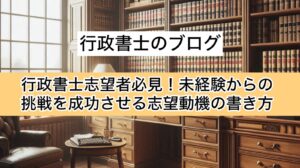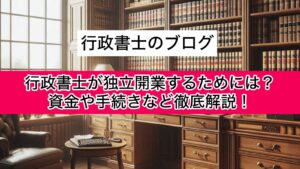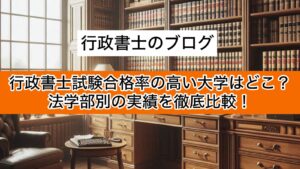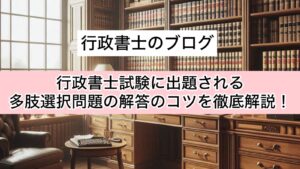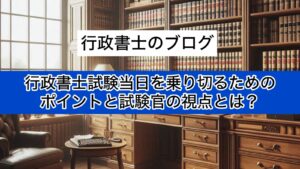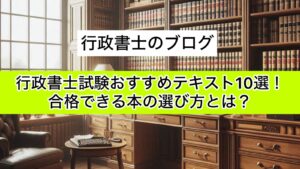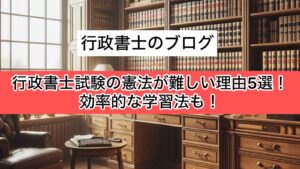行政書士を目指してる方が、実際に行政書士になったら、どんな事を依頼をされる事が多いのか、気になる方は多いのではないでしょうか?
行政書士の仕事って少しイメージしづらいですよね。
でも実際には、会社設立や許認可申請、遺言書や相続関係のサポート、さらには外国人の方のビザ申請など、幅広いお手伝いが可能なんです。
そこで、今回の記事では、行政書士にどんな事を依頼できるのか、ざっと簡単に一般的なサービス内容や手続きなどをまとめてみましたので、参考にして頂けたら幸いです。
数が結構ありすぎるので、「こういう事を依頼できるんだ~」と言う感じで気軽に見ていただけたらと思います!
行政書士が依頼されるサービス内容・手続きとは?
行政書士にはどんなことを依頼されるのか、ご紹介していきたいと思います!
依頼できる内容①:飲食店営業許可申請
行政書士に依頼できる内容1つ目は、飲食店営業許可申請です!
飲食店を開業するには、保健所から飲食店営業許可を取得する必要があります。
この許可がないと営業できませんし、食品衛生法違反となってしまいます。
依頼者としては、これから飲食店を始めたいオーナー様や法人の代表者が多く、「どんな書類が必要なのか」「施設基準を満たしているか不安」といった相談がよくあります。
手続きの流れとしては、まず保健所に事前相談を行い、必要な書類や施設基準を確認します。
その後、申請書類を揃えて提出します。
主な書類には、営業許可申請書、店舗の図面(平面図や設備配置図など)、食品衛生責任者資格証の写し、従業員の健康診断結果などがあります。
また、水質検査結果が必要な場合もあるので注意が必要です。
申請後は保健所による現地調査が行われ、問題がなければ許可証が交付されます。
行政書士としては、こうした書類作成や保健所との調整を代行し、依頼者様がスムーズに手続きを進められるようサポートするのが役割です。
依頼できる内容②:建設業許可申請
行政書士が依頼できる内容2つ目は、建設業許可申請です!
建設業を始めるには、一定の規模以上の工事を請け負う場合に建設業許可が必要です。
依頼者としては、これから事業を始めたい法人や個人事業主の方、あるいは新たな業種で許可を取得したいと考える会社の代表者が多いです。
「どの許可が必要なのか」「要件を満たしているか不安」といった相談がよくあります。
手続きの流れとしては、まず「一般建設業」か「特定建設業」か、さらに「知事許可」か「大臣許可」かを確認します。
その後、必要書類を揃えて申請します。
書類には、申請書や工事経歴書、財務諸表、専任技術者や経営業務管理責任者の証明書などがあります。
また、申請後には審査が行われ、問題がなければ1~2ヶ月程度で許可通知書が交付されます。
行政書士としては、こうした複雑な書類作成や役所との調整を代行するのが役割です。
依頼できる内容③:古物商許可申請
行政書士が依頼できる内容3つ目は、古物商許可申請です!
リサイクルショップや中古品の売買を始めるには、古物商の許可が必要です。
この申請は、個人事業主の方や法人の代表者から「どんな書類が必要なのか」「手続きが複雑で不安」といった相談を受けることが多いです。
手続きの流れとしては、まず営業所の所在地を管轄する警察署に相談します。
必要書類には、申請書、住民票(本籍地記載)、身分証明書、略歴書、誓約書などがあります。
また、営業所の見取り図や周辺地図も求められます。
法人の場合は定款や登記事項証明書も必要です。
さらに、インターネットで販売する場合はURL使用権を証明する資料も準備します。
行政書士としては、こうした書類作成や警察署との調整を代行し、依頼者様がスムーズに手続きを進められるようサポートするのが役割です。
依頼できる内容④:風俗営業許可申請
行政書士が依頼できる内容4つ目は、風俗営業許可申請です!
スナックやバー、クラブなどを開業する際には、警察署で風俗営業許可を取得する必要があります。
依頼者としては、これから店舗を始めたいオーナー様や法人の代表者が多く、「どんな書類が必要なのか」「基準を満たしているか不安」といった相談がよく寄せられます。
手続きの流れとしては、まず店舗の場所が許可を受けられる地域かどうか調査します。
その後、申請書や住民票、身分証明書、店舗の図面など必要書類を揃えます。
法人の場合は定款や登記事項証明書も求められます。
また、飲食物を提供する場合は保健所の営業許可も必要です。
申請後には警察による実地調査があり、問題がなければ許可証が交付されます。
行政書士としては、こうした複雑な手続きを代行し、依頼者様がスムーズに進められるようサポートするのが役割です。
依頼できる内容⑤:旅館業許可申請
行政書士が依頼できる内容5つ目は、旅館業許可申請です!
旅館やホテル、ゲストハウスなどの宿泊施設を営業するには、保健所から旅館業許可を取得する必要があります。
依頼者としては、これから宿泊業を始めたいオーナー様や法人の代表者が多いです。
「どんな手続きをすればいいのか」「施設が基準を満たしているか不安」といった相談がよくあります。
手続きの流れとしては、まず用途地域の確認や保健所への事前相談からスタートします。
その後、施設の図面作成や消防法に基づく設備検査などを進め、必要書類を揃えて申請します。
審査期間中には保健所による現地調査も行われます。
行政書士としては、こうした複雑な手続きを代行し、書類作成や役所との調整を行うことが主な役割です。
依頼できる内容⑥:動物取扱業(ペット関連)許可申請
行政書士が依頼できる内容6つ目は、動物取扱業(ペット関連)許可申請です!
ペットショップやトリミングサロン、動物の訓練施設などを始めるには、動物取扱業の許可が必要です。
この申請は、オーナー様や法人の代表者から「どんな書類が必要なのか」「基準を満たしているか不安」といった相談を受けることが多いです。
手続きの流れとしては、まず管轄の保健所や動物愛護センターに事前相談を行い、必要書類を確認します。
申請書や飼養施設の図面、動物取扱責任者の資格証明書などを揃えたうえで提出します。
また、犬や猫を扱う場合には「健康安全計画」の提出も求められることがあります。
さらに、施設が基準を満たしているか現地調査も行われます。
行政書士としては、こうした書類作成や役所との調整を代行し、依頼者様がスムーズに手続きを進められるようサポートするのが役割です。
依頼できる内容⑦: 産業廃棄物処理業許可申請
行政書士が依頼できる内容7つ目は、産業廃棄物処理業許可申請です!
この許可が必要になるのは、産業廃棄物の収集運搬や処分を事業として行う場合です。
依頼者としては、運送業者や廃棄物処理を新たに始めたい企業の社長さん、あるいは事業拡大を考えている法人の代表者が多いです。
「どんな書類が必要か」「基準を満たしているか」といった相談がよくあります。
手続きの流れとしては、まず自治体の担当窓口に事前相談を行います。
その後、申請書や事業計画書、運搬車両や保管施設の写真、財務書類などを揃えて提出します。
また、産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会の修了証も必要です。
さらに、施設や車両が基準を満たしているか現地調査も行われます。
行政書士としては、こうした複雑な書類作成や自治体との調整を代行するのが役割です。
依頼できる内容⑧:酒類販売業免許申請
行政書士が依頼できる内容8つ目は、酒類販売業免許申請です!
お酒を販売するには、税務署から酒類販売業免許を取得する必要があります。
依頼者としては、これから酒屋や飲食店での酒類販売を始めたいオーナー様や法人の代表者が多いです。
「どんな書類が必要なのか」「審査に通るか不安」といった相談がよく寄せられます。
手続きの流れとしては、まず税務署に相談し、必要書類を確認します。
例えば、申請書や住民票(法人の場合は登記事項証明書)、履歴書、土地・建物の登記事項証明書、納税証明書などが必要です。
また、「酒類販売管理者研修」の受講証も求められるので事前に準備が必要です。
さらに、事業計画や収支見込みを記載した書類も提出します。
行政書士としては、こうした複雑な書類作成や税務署との調整を代行し、依頼者様がスムーズに手続きを進められるようサポートするのが役割です。
依頼できる内容⑨:一般貨物自動車運送事業許可申請
行政書士が依頼できる内容9つ目は、一般貨物自動車運送事業許可申請です!
この許可は、トラックなどを使って有償で貨物を運ぶ事業を行う際に必要です。
依頼者としては、新たに運送業を始めたい法人や個人事業主の方が多く、「どこから手をつければいいのか」「書類が多くて不安」といった相談がよくあります。
手続きの流れとしては、まず営業所や車庫、車両が基準を満たしているか確認し、必要書類を揃えます。
例えば、申請書や事業計画書、車両や施設の使用権原を証する書類などが必要です。
また、申請後には役員法令試験があり、これに合格しないと許可が下りません。
さらに、許可後も運賃届出や車両登録(緑ナンバー取得)、運行管理者・整備管理者の選任届提出など、多くの手続きがあります。
行政書士としては、こうした複雑な書類作成や運輸支局との調整を代行するのが役割です。
依頼できる内容⑩:特殊車両通行許可申請
行政書士が依頼できる内容10個目は、特殊車両通行許可申請です!
この許可は、一般的な制限値を超える車両(大型トラックやクレーン車など)が道路を走行する際に必要です。
依頼者としては、運送業者や建設会社の方が多く、「どの書類を揃えればいいのか」「申請が複雑で困っている」といった相談がよくあります。
手続きの流れとしては、まず走行予定の道路管理者(国道事務所や県土木事務所など)に申請します。
必要書類には、特殊車両通行許可申請書、車両諸元に関する説明書、自動車検査証の写し、通行経路図などがあります。
また、走行経路が複数の道路管理者にまたがる場合は、一つの窓口でまとめて申請できます。
申請方法はオンラインと窓口提出があり、オンラインは特に国道を走行する場合に便利です。
行政書士としては、こうした書類作成や経路の確認を代行し、依頼者様がスムーズに許可を取得できるようサポートするのが役割です。
依頼できる内容⑪:株式会社や合同会社などの法人設立手続き
行政書士が依頼できる内容11個目は、株式会社や合同会社などの法人設立手続きです!
会社を設立するには、法務局で法人登記を行う必要があります。
依頼者としては、これから事業を始めたい個人事業主の方や法人化を検討している企業の代表者が多いです。
「どんな書類が必要なのか」「手続きが複雑で不安」といった相談を受けることがよくあります。
手続きの流れとしては、まず会社の基本事項を決めるところから始まります。
例えば、社名(商号)、所在地、資本金、事業目的、役員構成などですね。
その後、定款を作成し、公証役場で認証を受けます。
次に資本金を銀行口座に払い込み、設立登記申請書や定款謄本、資本金の払込証明書など必要書類を法務局に提出します。
登記が完了すれば法人設立となります。
行政書士としては、こうした複雑な書類作成や法務局との調整を代行し、依頼者様がスムーズに手続きを進められるようサポートするのが役割です。
依頼できる内容⑫:NPO法人、一般社団法人、一般財団法人の設立手続き
行政書士が依頼できる内容12個目は、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人の設立手続きです!
これらの法人は、それぞれ目的や運営形態が異なりますが、いずれも法務局での登記が必要です。
依頼者としては、地域貢献や社会活動を目的とした法人を立ち上げたい方や、事業の透明性を高めたい企業の代表者が多いです。
「どの法人形態が適しているのか」「手続きが複雑で不安」といった相談を受けることがよくあります。
まず、NPO法人は、特定非営利活動を行うための法人です。
設立には所轄庁(都道府県や市区町村)での認証が必要で、定款作成、役員名簿、設立趣意書、事業計画書などを提出します。
その後、「縦覧」と呼ばれる市民による閲覧期間や審査を経て認証されますので、認証後に法務局で登記を行い、正式に設立となります。
一般社団法人は、営利目的でも非営利目的でも設立可能な法人形態です。
社員2名以上と理事1名以上を確保し、定款を作成して公証人役場で認証を受けます。
その後、法務局に登記申請書や定款、役員選任書類などを提出して設立します。
比較的設立しやすいのが特徴です。
次に、一般財団法人は、一定の財産を基礎として公益活動などを行うための法人です。
設立には基本財産(通常300万円以上)が必要で、一般社団法人と同様に定款作成、公証人認証、法務局への登記手続きが必要です。
行政書士としては、それぞれの法人形態に応じた書類作成や役所との調整を代行し、依頼者様がスムーズに手続きを進められるようサポートするのが役割です。
依頼できる内容⑬:定款作成および電子定款対応
行政書士が依頼できる内容13個目は、定款作成および電子定款対応です!
会社や法人を設立する際に必要不可欠なのが「定款」です。
定款は、いわば会社や法人のルールブックで、設立手続きの最初のステップとなります。
依頼者としては、これから法人を立ち上げたい個人事業主の方や、会社設立を検討している法人の代表者が多いです。
「どんな内容を盛り込めばいいのか」「電子定款って何?」といった相談を受けることがよくあります。
ちなみに定款作成はどんな事をするのかと言うと、会社名(商号)、事業目的、本店所在地、資本金、役員構成など、会社運営に関する基本事項を記載します。
また、株式譲渡制限や決算期など、将来の運営に影響を与える重要な項目も含まれます。特に事業目的は曖昧な表現だと法務局で受理されないこともあるため、適切な記載が求められます。
又、電子定款に関してですが、紙ではなくデータ形式で作成された定款のことです。
紙の定款の場合は印紙代として4万円が必要ですが、電子定款にするとこの印紙代が不要になります。
そのため、コスト削減を考える方には電子定款対応がおすすめです。
ただし、電子署名や専用ソフトが必要になるため、自分で対応するのは少しハードルが高いと感じる方も多いです。
行政書士としてのサポート 行政書士としては、依頼者様のご要望をヒアリングしながら適切な内容で定款を作成するのが役割です。
依頼できる内容⑭:遺言書の作成支援(自筆証書遺言、公正証書遺言)
行政書士が依頼できる内容14個目は、遺言書の作成支援(自筆証書遺言、公正証書遺言)です!
遺言書は、財産の分配や相続に関する意思を明確に残すために重要なものです。
依頼者としては、将来の相続トラブルを防ぎたい方や、特定の相続人や団体に財産を遺贈したいと考える方が多くいらっしゃっていて、「どちらの形式が良いのか」「手続きが複雑で不安」といった相談がよく寄せられます。
自筆証書遺言の場合、遺言者自身が全文を手書きで作成する形式になります。
財産目録はパソコンで作成しても構いませんが、本文はすべて自筆である必要がありますので、日付、氏名、押印を忘れず記載し、訂正箇所には訂正印と署名を添える必要があります。
この形式は費用がかからず手軽ですが、紛失や偽造のリスクがあるため、法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用することもおすすめです。
公正証書遺言の場合は、公証人が遺言者の口述内容を基に作成する形式で、法的効力が高く安全性に優れています。
まず公証役場に相談し、財産目録や戸籍謄本など必要書類を提出します。
その後、公証人が文案を作成し、修正を経て確定します。
当日は公証役場で公証人と証人2名立会いのもと署名・押印を行います。
この形式は費用がかかりますが、紛失や改ざんの心配がありません。
行政書士としては、自筆証書遺言では適切な内容や形式で作成できるようアドバイスし、公正証書遺言では必要書類の準備や公証役場との調整を代行することが役割です。
依頼できる内容⑮:遺産分割協議書の作成
行政書士が依頼できる内容15個目は、遺産分割協議書の作成です!
相続が発生した際、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、その内容を書面にまとめたものが遺産分割協議書です。
この書類は、不動産の名義変更や預貯金の解約・名義変更などに必要となります。
依頼者としては、「相続人間で話し合いがまとまったけど、書類の作成方法がわからない」という方や、「法律的に正しい形で残したい」という方が多いです。
遺産分割協議書は、相続人全員が合意した遺産の分配内容を明文化したものです。
これには、不動産や預貯金、株式などの財産を誰がどのように相続するかを具体的に記載します。
また、相続人全員の署名・押印(実印)が必要で、印鑑証明書も添付します。
この書類がないと、不動産登記や金融機関での手続きが進められない場合があります。
作成時の注意点 遺産分割協議書は、内容が曖昧だったり、法律に反していたりすると無効になる可能性があります。
例えば、相続人全員の合意が取れていない場合や、法定相続分を無視した内容になっている場合などです。
また、不動産について記載する際は、登記事項証明書を基に正確な情報を記載する必要があります。
行政書士としては、依頼者様から財産や相続人についての情報をヒアリングし、法律に基づいた適切な内容で遺産分割協議書を作成するのが役割です。
依頼できる内容⑯:相続財産目録の作成
行政書士が依頼できる内容16個目は、相続財産目録の作成です!
相続財産目録は、相続が発生した際に被相続人(亡くなられた方)の財産を一覧にまとめた書類です。
これを作成することで、相続人間での遺産分割協議や相続税の申告手続きがスムーズになります。
依頼者としては、「財産の全体像を把握したい」「どこから手をつければいいかわからない」といった方が多いです。
相続財産目録は、不動産、預貯金、株式、生命保険、車両などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払い税金といったマイナスの財産も記載します。
不動産の場合は登記事項証明書や固定資産評価証明書を基に正確な情報を記載し、預貯金は通帳や残高証明書から確認します。
また、株式や投資信託なども時価を調べて記載します。
財産目録を作成する際には、漏れがないように被相続人の財産を徹底的に洗い出すことが重要です。
例えば、不動産や預貯金だけでなく、貸付金や未払いの公共料金なども含めます。
また、借金やローンなどの負債も正確に記載する必要がありますので、これを怠ると、後々トラブルになる可能性があるので注意が必要です。
行政書士としては、依頼者様から提供された資料を基に正確な財産目録を作成するお手伝いをします。
依頼できる内容⑰:遺言執行手続きのサポート
行政書士が依頼できる内容17個目は、遺言執行手続きのサポートです!
遺言書に書かれた内容を実現するための手続きです。
依頼者としては、「何から始めればいいのかわからない」「手続きが複雑で負担が大きい」といった方が多いです。
遺言執行手続きには、相続人や財産の調査、財産の名義変更や分配、特定の指示事項の実現などが含まれます。
例えば、不動産の名義変更には登記事項証明書が必要で、預貯金の解約には相続人全員の同意書が求められます。
また、遺留分への配慮も重要です。
行政書士としては、依頼者様からヒアリングを行い、必要な手続きを代行またはサポートします。
依頼できる内容⑱:離婚協議書の作成サポート
行政書士が依頼できる内容18個目は、離婚協議書の作成サポートです!
離婚協議書は、夫婦間で話し合った離婚条件を文書にまとめたものです。
依頼者としては、「養育費や財産分与をきちんと取り決めたい」「後々のトラブルを防ぎたい」という方が多いです。
協議書には、財産分与、養育費、親権、面会交流、慰謝料など具体的な内容を記載します。
特に養育費や財産分与の取り決めは曖昧にせず、金額や支払方法を明確にすることが重要です。
また、公正証書にしておくと、支払いが滞った際に強制執行が可能になるため安心です。
行政書士としては、依頼者様の希望を丁寧にヒアリングし、法的に有効な協議書を作成するお手伝いをします。
依頼できる内容⑲:離婚協議書の公正証書化サポート
行政書士が依頼できる内容19個目は、離婚協議書の公正証書化サポートです!
公正証書にすることで、養育費や財産分与などの取り決めに法的拘束力を持たせ、相手が約束を守らない場合でも裁判なしで強制執行が可能になります。
手続きとしては、夫婦で合意した内容を離婚協議書にまとめたうえで、公証役場に申し込みます。
必要書類には、実印、印鑑証明書、戸籍謄本、不動産登記簿謄本などがあります。
公証人が内容を確認し、公正証書を作成しますが、事前予約が必要です。
行政書士としては、協議書の内容確認から公証役場との調整までをサポートし、「これで安心」と思っていただけるよう丁寧に対応します。
依頼できる内容⑳:養育費や面会交流に関する合意書作成
行政書士が依頼できる内容20個目は、養育費や面会交流に関する合意書作成です!
離婚後の子どもの養育費や面会交流の取り決めを文書に残すことで、双方が合意内容を明確にし、トラブルを防ぐことができます。
依頼者としては、「将来の支払いが滞らないようにしたい」「面会交流のルールをきちんと決めたい」という方が多いです。
合意書には、養育費の金額や支払方法、支払期間、面会交流の頻度や方法などを具体的に記載します。
特に曖昧な表現は避け、双方が納得できる内容にすることが重要です。
また、公正証書化することで法的拘束力を持たせることも可能です。
行政書士としては、依頼者様の希望を丁寧にヒアリングし、法的に有効な合意書を作成するお手伝いをします。
依頼できる内容㉑:離婚後の戸籍変更や住民票移動などの行政手続き支援
行政書士が依頼できる内容21個目は、離婚後の戸籍変更や住民票移動などの行政手続き支援 です!
離婚後の戸籍変更や住民票移動などの行政手続き支援についてお話ししますね。
離婚後は、戸籍や住民票の変更など、さまざまな行政手続きが必要になります。
依頼者としては、「手続きが多くて何をすればいいかわからない」「役所での手続きが不安」という方が多いです。
具体的には、離婚届提出後に戸籍を変更する場合、転籍届や新しい戸籍の作成手続きが必要です。
また、住所を変更する場合は住民票の移動手続きを行います。
さらに、子どもの親権者が変わる場合は、子どもの戸籍変更も行う必要があります。
行政書士としては、必要な書類や手続きの流れをわかりやすく説明し、役所への申請書類作成をサポートします。
依頼できる内容㉒:在留資格(ビザ)申請・更新手続き
行政書士が依頼できる内容22個目は、在留資格(ビザ)申請・更新手続きです!
在留資格(ビザ)申請・更新手続きについてお話しします。
外国人が日本で活動を続けるためには、在留資格の取得や更新が必要です。
依頼者としては、「必要書類が多くて不安」「手続きが複雑」と感じる方が多いです。
新規申請では「在留資格認定証明書」の交付申請が必要で、受け入れ企業や代理人が入国管理局で手続きを行います。
更新の場合は、在留期間満了の3か月前から申請可能で、申請書、在留カード、活動内容を証明する書類などを提出します。
許可後には収入印紙代4,000円が必要です。
行政書士としては、必要書類の準備から申請手続きの代行までサポートし、「これで安心」と思っていただけるよう丁寧に対応します。
依頼できる内容㉓:永住許可申請
行政書士が依頼できる内容23個目は、永住許可申請です!
永住権を取得するには、「素行が善良」「安定した収入・資産」「日本国の利益に合致」といった要件を満たす必要があります。
また、原則として10年以上の日本滞在が求められます。
申請には、永住許可申請書、写真、在留カード、住民票、職業や所得を証明する書類、理由書などを準備し、入国管理局に提出します。
現在の在留資格によって必要書類が異なるため注意が必要です。
行政書士としては、書類作成や手続き代行を通じて申請者様がスムーズに進められるようサポートします。
依頼できる内容㉔:帰化申請手続きサポート
行政書士が依頼できる内容24個目は、帰化申請手続きサポート です!
日本国籍を取得するための帰化申請は、法務局での相談から始まり、書類収集、申請書作成、面接など多くのステップを経る必要があります。
依頼者としては、「手続きが複雑で不安」「必要書類が多くて大変」と感じる方が多いです。
申請には、帰化許可申請書、住民票、国籍証明書、納税証明書など多岐にわたる書類が必要です。
また、居住歴や収入の証明、生計の概要なども求められるため、準備に時間がかかります。
審査には1年以上かかることもあります。
行政書士としては、書類作成や収集を代行し、不備なくスムーズに手続きを進められるようサポートします。
依頼できる内容㉕:農地転用許可申請
行政書士が依頼できる内容25個目は、農地転用許可申請です!
農地を宅地や駐車場などに転用するには、農地法に基づく許可申請が必要です。
依頼者としては、「手続きが複雑」「必要書類が多い」と感じる方が多いです。
手続きは、農業委員会への申請書提出から始まり、知事や市町村長の許可を得る流れです。
必要書類には、登記事項証明書、公図の写し、位置図、事業計画書などが含まれます。
また、転用規模や地域によって手続き内容が異なるため、事前の確認が重要です。
行政書士としては、書類作成や役所との調整を代行し、「これで安心」と思っていただけるようサポートします。
依頼できる内容㉖:用途区分変更申出手続き
行政書士が依頼できる内容26個目は、用途区分変更申出手続きです!
農用地を他の用途に変更する際には、農業振興地域整備計画の変更手続きが必要です。
依頼者としては、「手続きが複雑で不安」「必要書類が多い」と感じる方が多いです。
申出には、用途区分変更申出書、位置図、土地利用計画図、公図、登記事項証明書、事業計画書などの書類を準備し、農業委員会や市町村に提出します。
計画面積が1ヘクタールを超えないことや、他の農地利用に支障がないことなどが条件となります。
行政書士としては、必要書類の作成や役所との調整を代行し、「これで安心」と思っていただけるようサポートします。
依頼できる内容㉗:車庫証明取得代行
行政書士が依頼できる内容27個目は、車庫証明取得代行です!
車庫証明は、自動車の保管場所が確保されていることを証明する書類で、警察署で申請します。
依頼者としては、「手続きが面倒」「必要書類の準備が難しい」と感じる方が多いです。
申請には、自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書、所在図・配置図、保管場所使用承諾証明書(または自認書)などが必要です。
警察署での受付時間は平日のみで、交付までに3~7日かかります。
行政書士としては、書類作成や警察署への申請を代行し、「これで安心」と思っていただけるようサポートします。
依頼できる内容㉘:自動車登録
行政書士が依頼できる内容28個目は、自動車登録です!
自動車を公道で走らせるためには、運輸支局や検査登録事務所で登録手続きを行い、ナンバープレートを取得する必要があります。
依頼者としては、「手続きが複雑」「時間が取れない」と感じる方が多いです。
登録には、申請書、印鑑証明書、委任状、自動車保管場所証明書、譲渡証明書などの書類が必要です。
また、新車の場合は完成検査終了証、中古車の場合は予備検査証や保安基準適合証などが求められます。
手数料納付や重量税印紙の購入も必要です。
行政書士としては、書類作成や陸運支局への申請を代行し、「これで安心」と思っていただけるようサポートします。
依頼できる内容㉙:各種契約書の作成
行政書士が依頼できる内容29個目は、各種契約書の作成です!
契約書は、取引や合意内容を明確にし、トラブルを防ぐために重要な書類です。
依頼者としては、「法的に有効な内容にしたい」「自分で作成するのが難しい」という方が多いです。
作成する契約書には、売買契約書、賃貸借契約書、業務委託契約書、秘密保持契約書(NDA)などがあります。
それぞれの契約内容に応じて、権利義務や条件を具体的かつ明確に記載する必要があります。
また、曖昧な表現を避け、将来の紛争リスクを軽減することが大切です。
行政書士としては、依頼者様のご要望を丁寧にヒアリングし、適切な契約内容を反映した書類を作成します。
依頼できる内容㉚:内容証明郵便の作成
行政書士が依頼できる内容30個目は、内容証明郵便の作成です!
内容証明郵便は、相手に送った文書の内容や送付日時を公的に証明する手段で、主に契約解除や支払い請求、トラブル解決の際に利用されます。
依頼者としては、「法的に有効な形で通知したい」「文章作成が難しい」という方が多いです。
作成時には、事実関係を整理し、相手に伝える内容を簡潔かつ正確に記載することが重要です。
また、感情的な表現や曖昧な表現を避け、法的効力を持たせるための適切な文面を心掛けます。
郵便局での手続きも必要です。
行政書士としては、依頼者様の状況をヒアリングし、目的に合った内容証明文書を作成します。
依頼できる内容㉛:示談書、念書、合意書の作成
行政書士が依頼できる内容31個目は、示談書、念書、合意書の作成です!
これらの書類は、トラブルや紛争が発生した際に当事者間で合意した内容を文書化し、後々のトラブルを防ぐために重要です。依頼者としては、「法的効力を持たせたい」「内容を正確にまとめたい」という方が多いです。
示談書には、解決内容や条件を具体的に記載し、双方が納得できる形で締結します。
念書は約束事を簡潔に記載するもので、合意書は契約や取り決めの内容を明確にするための文書です。いずれも曖昧な表現を避け、法的リスクを軽減することが大切です。
行政書士としては、依頼者様の状況や希望を丁寧にヒアリングし、適切な文面で作成します。
依頼できる内容㉜:補助金・助成金申請サポート
行政書士が依頼できる内容32個目は、補助金・助成金申請サポートです!
補助金や助成金は、事業の成長や新しい取り組みを支援するための公的な資金ですが、申請には複雑な手続きが伴います。
依頼者としては、「要件がわかりにくい」「書類作成が難しい」と感じる方が多いです。
申請には、事業計画書や収支予算書、必要書類の準備が求められます。
また、申請要件を満たしているかを確認し、審査で通過するためのポイントを押さえることが重要です。
期限内に正確な書類を提出することも欠かせません。
行政書士としては、依頼者様の事業内容や目的に合った補助金・助成金を提案し、申請書類の作成や提出をサポートします。
依頼できる内容㉝:知的財産権に関する契約書作成
行政書士が依頼できる内容33個目は、知的財産権に関する契約書作成です!
著作権や商標権、特許権などの知的財産権に関する契約書は、権利の使用や譲渡、ライセンス契約を明確にし、トラブルを防ぐために重要です。
依頼者としては、「法的に有効な形で権利を守りたい」「内容を正確にまとめたい」という方が多いです。
契約書には、権利の範囲や使用条件、対価、期間、違反時の対応などを具体的に記載します。
曖昧な表現を避け、双方が納得できる内容にすることが重要です。
また、知的財産権の特殊性を理解した上で作成する必要があります。
行政書士としては、依頼者様の意向を丁寧にヒアリングし、適切な文面で契約書を作成します。
まとめ
今回は、行政書士にどんな事を依頼できる?サービス内容や手続など徹底解説!というテーマでご紹介しました!
行政書士に依頼できるのが、こんなにも沢山あるんだなと思うと、行政書士の仕事って大変だなと思ってしまいますよね。
ただ、これだけ幅広い業務を担えるということは、自分の得意分野や興味のある分野を活かして活躍できるチャンスが多いと言うことでもあります。
まずは、依頼できる内容を人通り目を通して、その中から、どれが自分の得意分野があるのか把握することが大事です。
資格取得までの道は難しいかもしれませんが、努力が必ず実を結びます。
ぜひ目標に向かって、一歩ずつ進んでくださいね。
最後までお読みいただいてありがとうございました!
それでは!