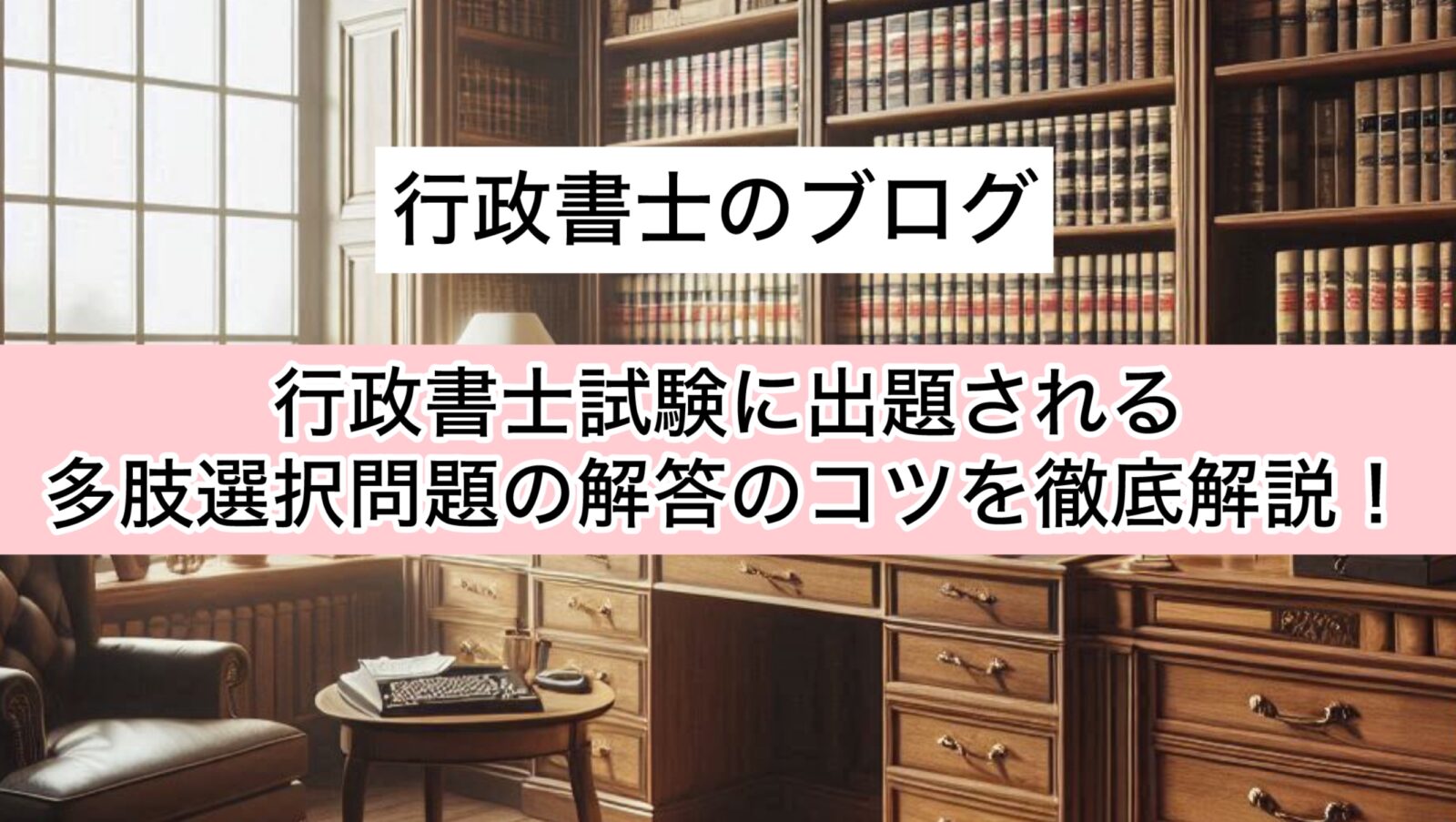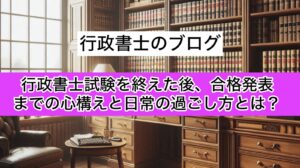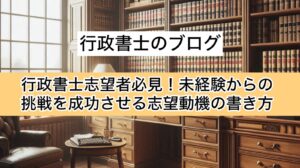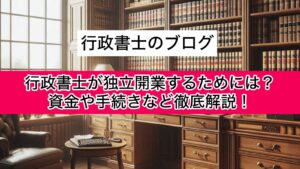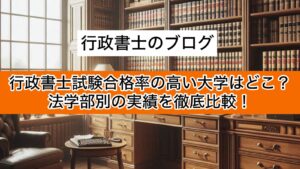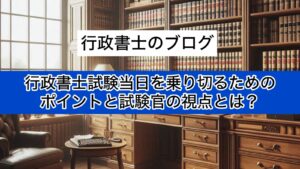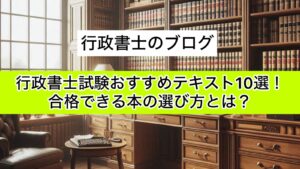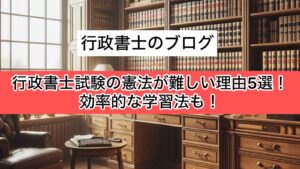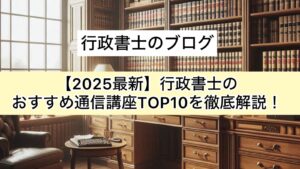行政書士試験の勉強を進める中で、多肢選択問題に苦戦している方も多いのではないでしょうか?
選択肢が多いと、どれを選べばいいのか迷ってしまうこともありますよね。
でも、ちょっとしたコツを押さえるだけで、解答の精度がぐんと上がるんです!
今回の記事では、多肢選択問題を攻略するための具体的なポイントや、試験本番で役立つテクニックをわかりやすく解説していきます。
ぜひ最後まで読んでいただき、試験対策にお役立てくださいね!
それではさっそく本題に入っていきましょう!
行政書士試験の多肢選択問題の特徴とは?
行政書士試験の多肢選択問題の特徴などをお伝えしていきます。
問題の種類と難易度
行政書士試験の多肢選択問題って、いわゆる「穴埋め問題」なんですよね。
私も初めて見たとき、「空欄が4つもあるのに、20個の語句から選ぶってどういうこと!?」ってびっくりしました。
でも、実際に取り組んでみると、憲法から1問、行政法から2問出題されるってパターンが決まっているので、慣れてくると少し安心感が出てきます。
難易度は、憲法の問題がちょっとクセモノで、初めて見る内容が出ることも多いですが、一方で、行政法は過去問から似たような出題が多いので、しっかり対策しておけば取りやすい印象です。
あと、多肢選択問題は部分点がもらえるんですよね。
だから、全部正解できなくても点数が入る可能性があるのはありがたいなと思います。
回答のポイントとは?
私の場合、多肢選択問題を解くときにはいくつか意識していたポイントがあります!
まず一つ目は、過去問を徹底的にやることです!
行政法なんかは特に過去問から似たような問題が出やすいので、過去問を繰り返し解くのが一番効率的だと思います。
私も実際に勉強している中で、「あ、この問題見たことある!」って思うことが結構ありましたし、そういうときはスムーズに答えられるので自信にもつながりました。
次に意識していたのが、消去法を使うことです。
20個も語句が並んでいると最初は圧倒されちゃうんですけど、「これは絶対違うな」っていうものをどんどん消していくと、残った選択肢から絞りやすくなるんですよね。
冷静に考えると意外と消せるものが多いので、焦らずに1つ1つ消していくのがポイントだと思います。
それから、文章を丁寧に読むことも大事です。
問題文にはヒントが隠れていることが多いので、とにかく焦らず丁寧に読むことを心がけていました。
特に空欄の前後をしっかり読んでみると、「あ、この言葉しか入らないな」って気づけることもあります。私の場合、焦って読み飛ばしてしまったことでミスした経験もあったので、それ以降はじっくり読むようにしていました。
最後に、絶対に諦めないことですね。
多肢選択問題は部分点があるので、わからない空欄でもとりあえず埋めておいたほうがいいです。
私も「これで合ってるかな?」って半信半疑で書いた答えが意外と当たっていたことが何度かありましたし、空欄のままにするより断然いい結果につながります。
多肢選択問題は最初は難しく感じるかもしれませんが、慣れてくれば得点源になると思いますので、焦らずコツコツ練習していけば必ず力になるので、一緒に頑張りましょう!
行政書士のための多肢選択問題解答戦略!
行政書士試験の多肢選択問題は、配点が高く、試験全体の中でも得点源になりやすい重要なパートです。
ただ、その形式が独特で、最初はどう解けばいいのか戸惑う方も多いと思いますが、私自身も最初は苦手意識がありましたが、コツを掴むことで徐々に得点力を上げることができました。
ここでは、基本的なアプローチと高得点を狙うためのテクニックをご紹介します!
基本的なアプローチ
まず、多肢選択問題に取り組む際に意識したいのは、「冷静さを保つこと」です。
問題文を見た瞬間に選択肢の多さに圧倒されることもありますが、慌てずに一つひとつ確認することが大切です。
私の場合、最初にやるのは問題文をしっかり読み込むことです。
空欄前後の文章や文脈からヒントを探し出し、「この空欄にはどんな語句が入るべきか」をイメージします。
そして次に、選択肢全体をざっと眺めてみます。
ここで重要なのは、「明らかに違うものを消していく」という消去法です。
20個もの語句から選ぶ形式ですが、実際には不適切な語句が目立つので、それらを除外していくだけでもかなり絞り込めます。
また、多肢選択問題は部分点があるので、わからない箇所があっても諦めずに埋めることがポイントです。
特に自信のある空欄から優先的に埋めていくと、他の空欄にもヒントが見えてくる場合があります。
これを繰り返していくことで、全体的な精度を上げることができます。
高得点を狙うためのテクニック
高得点を目指すには、基本的なアプローチだけでなく、さらに踏み込んだテクニックを活用することが重要ですので、私が実践して効果的だった方法をご紹介します。
まず一つ目は、過去問から傾向を掴むことです!
行政法の多肢選択問題では過去問から似たような内容が出題されることが多いため、過去問を繰り返し解いておくことで「出題パターン」が見えてきます。
「あ、この語句はよく使われるな」とか「こういう文脈ではこの言葉が正解になりやすい」といった感覚が身につくので、本番でも迷わず選べるようになります。
次におすすめなのは、時間配分を意識することです。
多肢選択問題は配点こそ高いものの、一問一問に時間をかけすぎてしまうと他の問題に影響が出てしまいます。
私の場合、「1問につき5~7分以内で解く」というルールを決めて取り組んでいました。
時間内で解けない場合は一旦飛ばして後回しにすることで、全体的なペース配分を守るよう心掛けました。
最後に、知識だけでなく感覚も鍛えることです。
多肢選択問題では知識だけでなく、「この語句なら文脈的にぴったりだな」といった直感的な判断も求められる場面があります。
そのためには普段から文章読解力や言葉の使い方への感覚を養っておくことが大切です。例えば憲法や行政法の条文を読む際にも「この言葉ってこういう場面で使われるんだ」と意識して読むと、本番でも役立つ場面が増えます。
これらのテクニックを活用することで、多肢選択問題は苦手な部分から得意分野へと変えることができます!
焦らずコツコツと練習して、自信を持って試験本番に挑みましょう!
行政書士試験で多肢選択問題を攻略するための準備方法!
多肢選択問題は行政書士試験の中でも配点が高く、試験全体の合否を左右する重要なパートです!
ただ、その形式が独特なので、しっかりとした準備が必要になりますので、ここでは、多肢選択問題を攻略するために私が実践していた学習計画の立て方や問題集の活用法についてお話しします。
学習計画の作成
まず、多肢選択問題を攻略するためには、全体的な学習計画の中でこのパートにどれくらい時間を割くかを決めることが大事です!
私の場合、最初は「多肢選択問題って難しそうだな」と思って後回しにしてしまったんですが、配点が高いことを考えると早めに取り組むべきだと気づきました。
具体的には、まず憲法と行政法の基本的な知識を固めることからスタートしました。
この2科目は多肢選択問題で出題される範囲なので、条文や判例を重点的に学習しました。
そして、多肢選択問題専用の勉強時間を週に2~3回設けて、過去問や問題集に取り組むようにしました。
ポイントは「最初から完璧を目指さないこと」です!
最初は間違えてもいいので、とにかく問題形式に慣れることを優先しましたし、また、学習計画には「復習の時間」を必ず組み込むようにしました。
一度解いた問題でも時間が経つと忘れてしまうので、間違えた問題や迷った問題はノートにまとめておいて、定期的に見返すようにしていました。
この復習サイクルのおかげで、自分の弱点が少しずつ克服できたと思います。
問題集の活用法
次に、多肢選択問題対策として欠かせないのが問題集です!
私の場合、「過去問」と「予想問題集」の2種類を使い分けていました。
まずは過去問ですが、行政法では特に過去問から似たような出題がされることが多いので、過去問は何度も繰り返し解きました。
ただ解くだけではなく、「なぜこの選択肢が正しいのか」「なぜ他の選択肢は間違っているのか」を丁寧に確認することで、知識が深まります。
また、過去問を解いていると出題傾向やよく使われる語句が見えてくるので、本番でも「あ、このパターンだ!」と気づけることが増えました。
次に予想問題集ですが、これは応用力を鍛えるために使いました。
予想問題集には過去問では見たことがないような新しい形式や語句も含まれているので、本番で初見の問題に対応する力をつけるためには最適でした。
私は予想問題集を解く際にも必ず解説まで読み込むようにして、「こういう文脈ではこの言葉が使われるんだ」といった感覚を養うよう意識していました。
さらに、間違えた問題や迷った問題は付箋やマーカーで印をつけておきました。
そして試験直前にはその部分だけを見返すことで効率よく復習できましたので、この方法は本当におすすめです!
多肢選択問題は最初は難しく感じるかもしれませんが、計画的な学習と効率的な問題集の活用で着実に力をつけることができますので、諦めずに頑張っていきましょうね!
まとめ
今回は、行政書士試験に出題される多肢選択問題の解答のコツを徹底解説!というテーマでご紹介しました!
多肢選択問題は行政書士試験において重要な得点源であり、独特な形式に慣れることが鍵です。
過去問の徹底的な活用や消去法の実践、そして問題文を丁寧に読み解く姿勢が高得点への近道となります。
また、時間配分や直感力を磨くことで、より効率的に解答できるようになります。
最初は難しく感じるかもしれませんが、計画的な学習と継続的な練習を重ねることで必ず克服できますので、一歩一歩着実に取り組み、自信を持って試験本番に臨みましょう!
最後までお読みいただいてありがとうございました!
それでは!