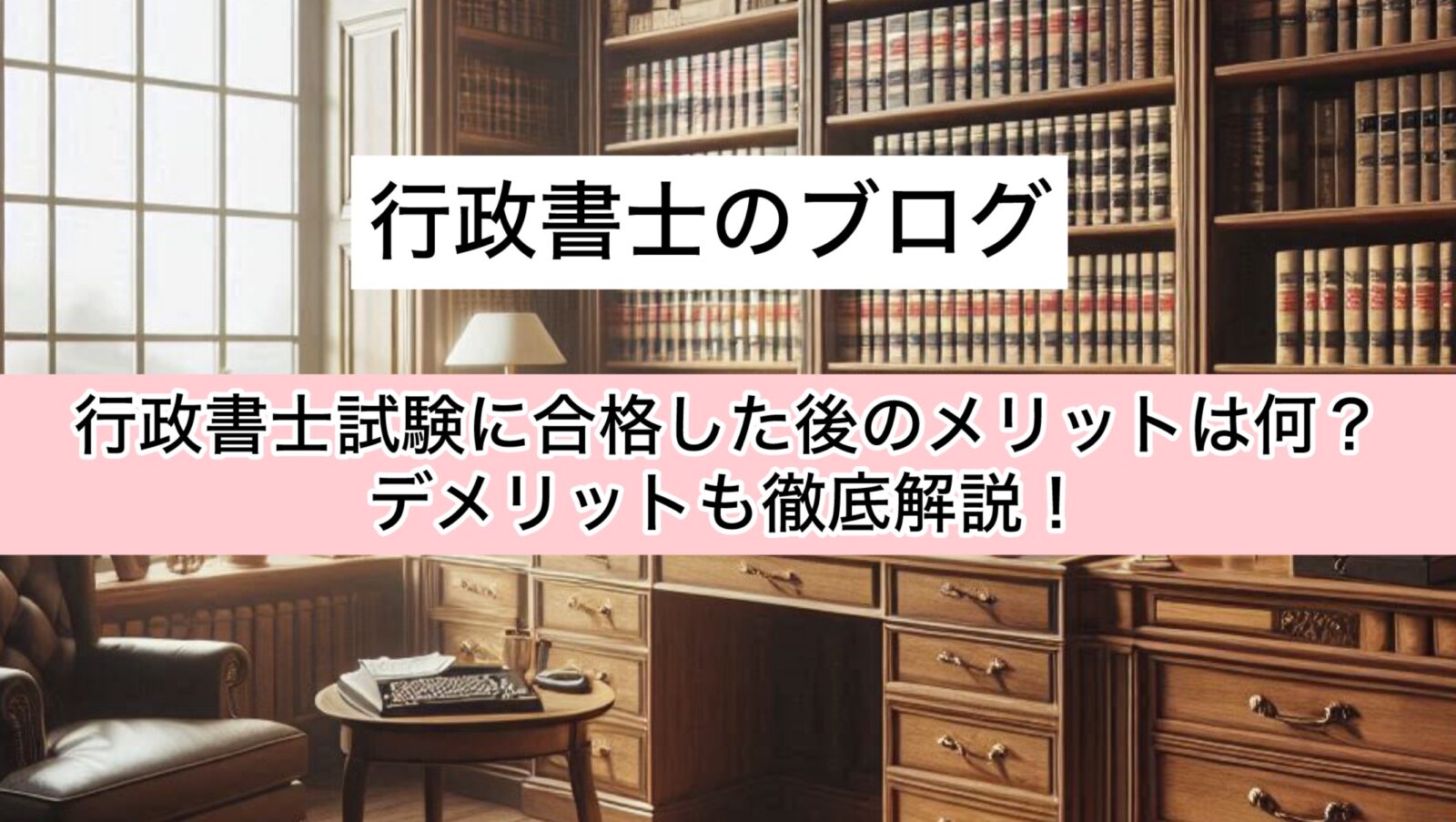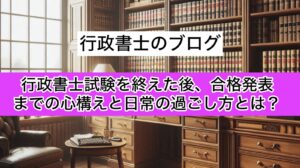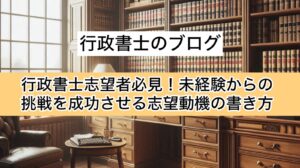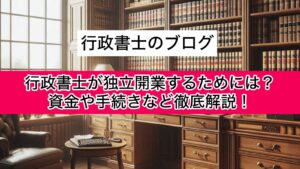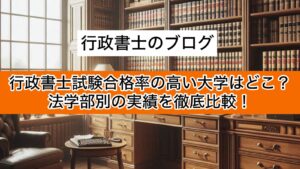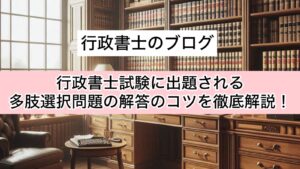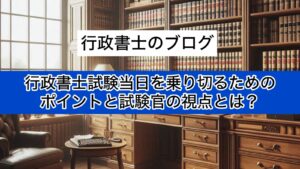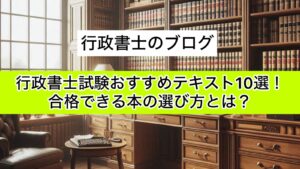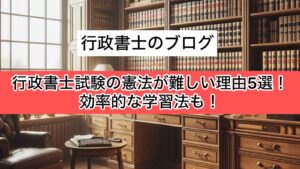行政書士試験を受験しようと思ったときに気になるのが、行政書士のメリットとデメリットですよね。一生懸命勉強して行政書士試験に合格したのはいいけれど、「こんなはずじゃなかったのに」と理想と現実のギャップにショックを受ける方も多いのではないでしょうか?今回は、そんな方に向けて、行政書士のメリットとデメリットについて、現役行政書士が詳しく解説していきます。
行政書士のメリット3選!
行政書士試験に合格後、本格的に行政書士として活動を行っていきますが、その後の活動でどういうメリットがあるのか、3つほどご紹介していきたいと思います!
メリット①:コストパフォーマンスが高い
まず1つ目のメリットは、行政書士はコストパフォーマンスが高いという点です。
これは行政書士をはじめとした専門職は、他のビジネスと比べて成功しやすいからです。独占業務が与えられている独立開業に向いている専門職の中では、行政書士が最も取得しやすい資格だと言えます。つまり、行政書士は成功しやすいビジネスの中で一番開業のハードルが低いのです。
例えば、年収1000万円を目指す場合、超難関資格と行政書士での開業を比較すると、超難関資格は資格を取得するための勉強だけで5000から1万時間かかりますが、行政書士の場合には約1000時間程度で資格を取得し、残りの4000から9000時間で年収1000万円を達成することは十分可能です。
つまり、超難関資格を目指している人が資格を取得して開業するまでに、行政書士であれば資格を取得して開業し、さらにビジネスで成果を出して目標達成するところまでいけるというわけです。しかも、行政書士だからといって超難関資格以上に稼げないわけではなく、経営戦略次第で他の超難関資格以上に稼ぐことも十分可能なので、ビジネス視点で見るとかなりコストパフォーマンスが高い資格だと言えます。
メリット②:信頼性が高い
次に2つ目のメリットは、信頼性が高いという点です。
一昔前までは行政書士は法律系の入門資格などと軽く見られることが多く、一般的な評価もそこまで高くはありませんでした。
しかし近年では試験の難しさが一般的に認知され、知名度が高く、法律系国家資格ということもあり、一般の方からの信頼性は高いと感じます。具体的な例でいうと、行政書士をしているというだけで「すごいですね」とか「試験難しいですよね」と言われることが多く、法律系国家資格ということで信頼性が担保されているため、ビジネスを一緒にやりませんかと声をかけていただけることも多いです。
また、一般的には個人事業主などと比べると、融資を受ける際や事務所を借りる際などの審査が通りやすいという点でも、世間的な信頼性は高く、ビジネスを進めていきやすいという点でメリットだと言えます。
メリット③:他のビジネスにつなげやすい
そして3つ目のメリットは、他のビジネスにつなげやすいという点です。
行政書士の仕事は建設業や外国人のビザ、会社設立、飲食業など、いろいろな業界と隣接しているため、同業他社と異なった集客経路やサービスでビジネスを組み立てやすいです。
例えば、ウェブ業界や人材業界は大手企業が乱立する激戦区ですが、会社設立と合わせてホームページの作成やウェブ集客の代行サービスを提供したり、就労ビザの申請と合わせて外国人材を紹介するなど、行政書士業務を起点としてビジネスを組み立てることで、その業界のライバルとは違った戦い方ができるようになります。
そうすることで、ライバルが真似できないビジネスモデルが確立でき、激戦区でも自分だけのブルーオーシャンでビジネスを進めていけます。しかも、行政書士が作成できる書類は1万種類と言われるほど多くの業界と隣接しているため、自分の知識や経験にあった独自のビジネスモデルを作ることができる可能性にあふれた職業だと言えるのではないでしょうか。
行政書士のデメリット4選!
行政書士の代表的なメリットを3つ程お伝えしてきましたが、ここからは行政書士のデメリットについて4つ程ご紹介していきたいと思います。
デメリット①:就職・転職に有利にならない
まず1つ目のデメリットは、行政書士の資格は就職・転職に有利にならないという点です。
一般的には資格を取得すると就職や転職に有利と言われていますが、行政書士に関しては有利になりません。
なぜなら、行政書士の知識は一般企業において役に立つ場面がかなり限定的だからです。例えば、簿記であれば経理に、社労士であれば人事や総務に、宅建であれば不動産の仕事に役立ちますが、行政書士の場合には許可の申請の知識はその企業が許可を取得できればその後は必要なくなりますし、契約書の作成についても一度作成すれば、その後は異なる契約内容が出てくるまでは必要ありません。
つまり、行政書士の知識が役に立つのはスポット的なので、行政書士の有資格者を雇うメリットが小さいのです。もちろん、行政書士事務所などの専門事務所に就職・転職するのであれば有利になりますし、資格取得の努力が評価されるかもしれませんが、それでも一般企業への就職や転職には有利に働きにくいので、これはデメリットだと言えます。
デメリット②:実務経験なしで開業しなければならない
次に2つ目のデメリットは、行政書士試験に合格した場合には実務経験なしで開業しなければならない点です。
他の専門職については、基本的には資格取得後にどこかの事務所に勤務し、実務経験を積んでから独立開業するケースが一般的ですが、行政書士に関してはそもそも行政書士事務所の求人がほとんどないため、実務経験を積む場所がなく、実務経験なしで即開業せざるを得ません。
もちろん、全く就職先がないというわけではなく、都心部であれば少しは行政書士の求人もありますが、それでも事務所に勤務してから開業する行政書士は全体のごく一部です。特に行政書士の業務は多岐にわたり、試験で勉強した内容とはまったく異なる仕事が多いため、開業当初は実務において苦労することがあるため、これもデメリットだと言えます。
しかし、逆に言うと、実務経験なしで即独立開業している人がほとんどということは、実務はネットや書籍で調べたり役所に聞いたりしてこなせるレベルであるため、そこまで心配する必要はありません。
デメリット:業務の差別化が難しい
次に3つ目のデメリットは、行政書士の業務は差別化が難しいという点です。
なぜなら、行政書士の主な業務は行政に提出する書類を作成することですが、行政手続きは公正の確保と透明性が必要であり、書類を作成した人によって許可が変わるような不公平な取り扱いはできません。
もちろん、裁量性が認められている処分もあるため、すべての申請において全く同じ処分がされるわけではありませんが、それでも弁護士のように「この人に依頼したら勝てるが、この人に依頼したら負ける」というようなことは起こりにくく、専門性での業務における差別化の難易度が高いと言えます。
つまり、他の事務所とうまく差別化できない場合には、価格競争に巻き込まれたり、仕事が取れずに廃業に追いやられてしまう可能性があるため、差別化が難しいというのは行政書士のデメリットだと言えます。
デメリット④:単発仕事が多く集客が大変
最後の4つ目のデメリットは、単発仕事が多く集客が大変という点です。
行政書士の仕事は単発的な依頼が多く、毎月新しい顧客を獲得し続けなければならず、営業力や集客力がなければ収益は安定しません。例えば、税理士や社労士などであれば顧問契約で毎月安定的に売り上げを確保できますが、行政書士の場合、今月の売り上げが100万円でも来月の売り上げがゼロになる可能性も十分にあります。
もちろん、工夫次第では行政書士でも顧問契約を結んだりすることで定期収入を作ることは可能ですが、それでも他の専門職と比べて集客の部分はかなり大変だと思います。
実際に開業する多くの行政書士が最も苦労する部分が実務ではなく集客の部分であり、行政書士が食えないと言われる理由もこの部分が大きく影響しています。ですので、営業やマーケティングが苦手な方にとっては、この点が行政書士の最大のデメリットではないでしょうか。
まとめ
今回は、行政書士試験合格した後のメリットは何?デメリットも徹底解説!と言うテーマでご紹介しました!
行政書士には確かにいろいろなデメリットもありますが、それを補って余りあるほどのメリットがあるので、個人的には行政書士はかなりおすすめだと思います。
そのため、デメリットを理解した上でしっかりと対策を講じれば、行政書士という資格は非常に大きな可能性を秘めた選択肢となります。
行政書士を目指してる方は、まずは地道にコツコツ勉強して努力することが大事なので、1つ1つの項目をしっかり知識を得て、試験の合格を目指して頑張っていきましょう!
最後までお読みいただいてありがとうございました!
それでは!